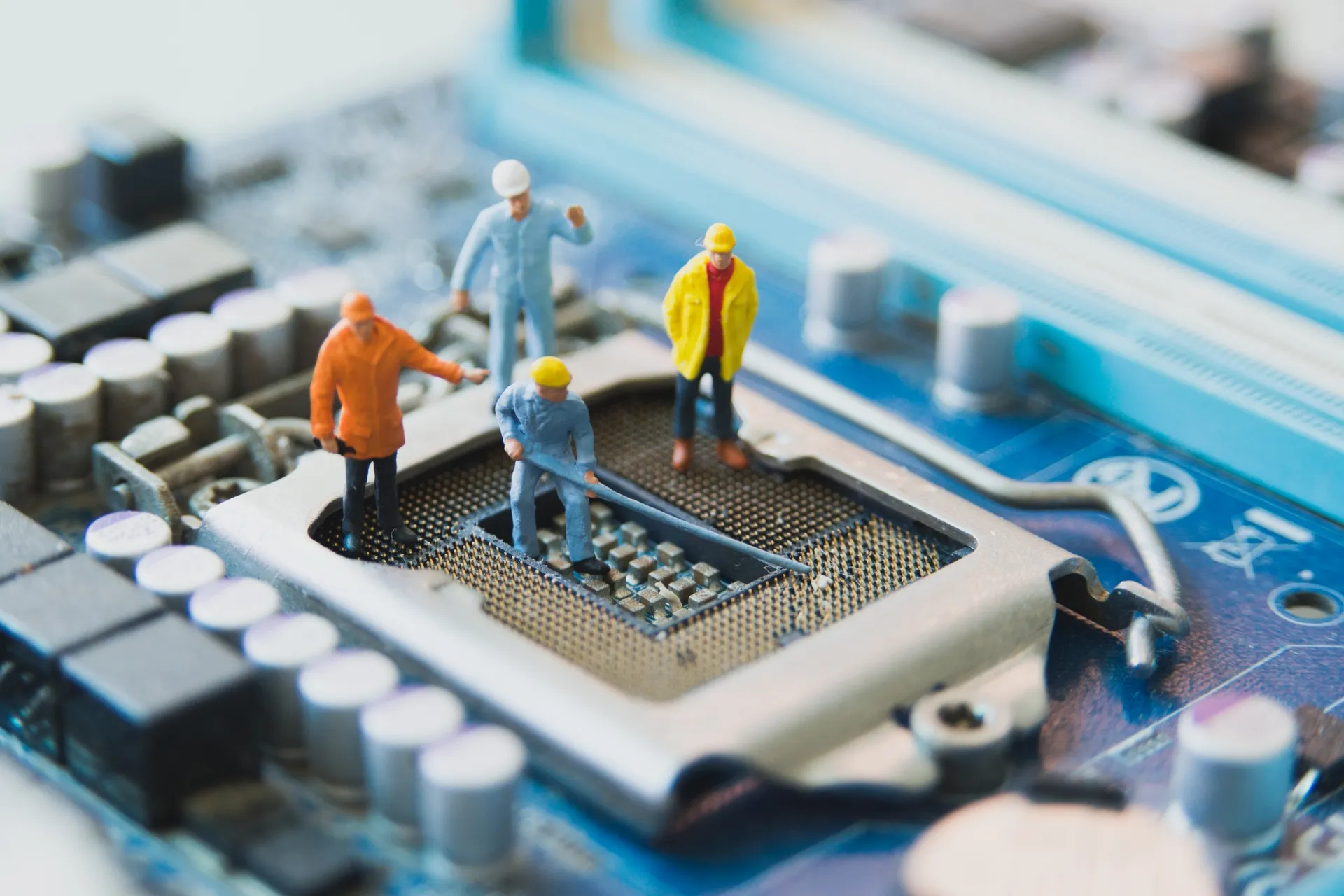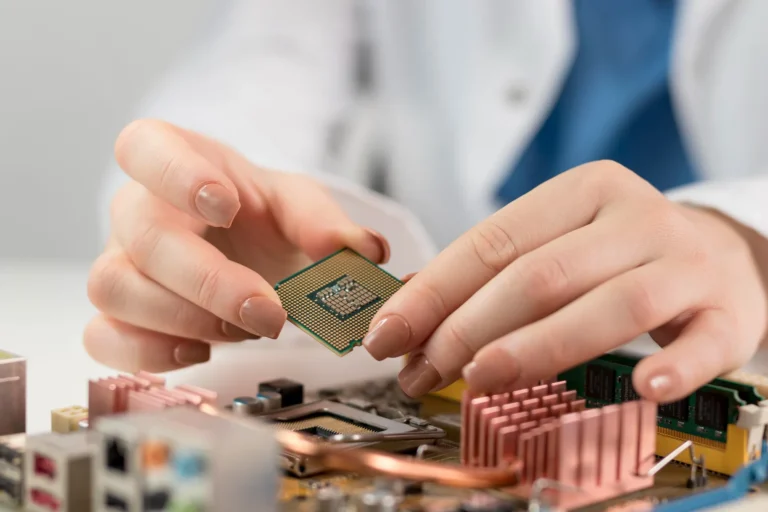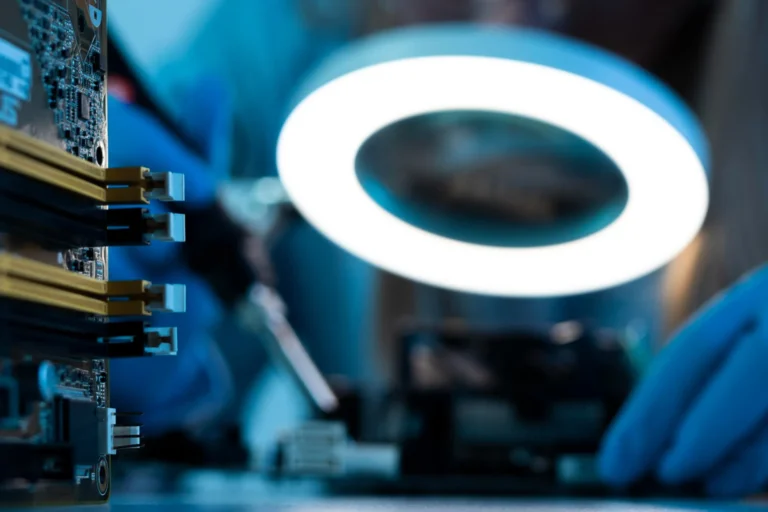チップレットと3Dメモリの進化が導く半導体設計の次世代
半導体技術の進化は、これまで「微細化」によって支えられてきました。しかし、ナノスケールに達した現在、物理的・技術的な限界が顕在化し、従来の延長線上では性能向上を維持することが困難になっています。
こうした背景の中で注目されているのが、「More Than Moore」と呼ばれる新たなアプローチです。これは、単なるトランジスタの微細化に依存せず、システム統合や立体構造の採用によって、機能性と高集積性を両立させる技術革新を指します。
本記事では、チップレット技術や3D NAND、今後期待されるDRAMの3次元化など、次世代の半導体実装技術について詳しく解説します。
チップレット技術による柔軟な集積設計
微細化の限界が迫る中、異なる回路や機能を持つチップを組み合わせて1つのパッケージに収める「チップレット技術」が、システム設計における柔軟性と効率性を大きく高めています。
従来のモノリシックな一体型設計とは異なり、用途や製造条件に応じた最適なチップ同士を組み合わせることで、歩留まり向上や開発の迅速化が可能となります。特にAIや高速処理を必要とする分野では、このアプローチが大規模集積の新たな選択肢として注目されているのです。
異種チップを統合するシステム・イン・パッケージ(SiP)
導体の微細化が物理的な限界に近づく中で、新たな性能向上手法として注目されているのが「More Than Moore」のアプローチです。その中核を成すのが、複数の機能を持つチップを一体化する「システム・イン・パッケージ(SiP)」です。従来は1つのチップ内にすべての機能を詰め込むSoC(System on Chip)が主流でしたが、SiPではプロセス技術や設計要件の異なるチップを分割し、それぞれを最適な形で製造・実装します。これにより、高性能CPU、AIアクセラレータ、メモリ、無線通信モジュールなどを同一パッケージ内で効率よく組み合わせることが可能になります。
中でも「チップレット」技術は、複数の小型チップをパッケージ基板上に並列配置し、短距離かつ高速な配線で接続する方式であり、最先端プロセスの適用が難しい周辺回路などを成熟したノードで作成できるのが特長です。異種混載による柔軟な設計が可能となり、コスト効率・熱特性・歩留まりの改善にも寄与します。このようなパッケージ技術は、今後の半導体進化を支える要素技術として、急速に普及が進んでいます。
チップレット技術のメリットと採用事例
チップレット技術は、異なる機能や製造プロセスを持つ複数の小型チップを1つのパッケージ内で統合することで、従来のモノリシックな大規模ICとは異なる柔軟性と効率性を実現する手法です。大きなメリットのひとつは、個別に製造されたチップから良品のみを選んで組み合わせることができる点にあり、全体としての歩留まりを大幅に改善できます。これにより、不良発生率の低下に伴うコスト削減も可能になります。
また、異なるノードや技術世代の混載が容易であるため、最先端プロセスが必要な演算部だけを微細化し、他の回路は成熟したプロセスで低コストに製造できるといった設計上の最適化も可能です。実際に、米Intelの「Core Ultra」シリーズではこの技術が採用され、AIアクセラレータ、GPU、I/O制御などの各チップレットを組み合わせることで、高性能と省電力の両立が図られています。今後もサーバー向けプロセッサや先端モバイルSoCを中心に、チップレットベースの設計が主流になると見られています。
NAND型フラッシュメモリとDRAMの3次元化
記憶容量の拡大と電気的特性の安定化を図るために、メモリ分野でも大きな構造転換が進められています。NAND型フラッシュメモリは、2010年代以降、セルの微細化に代わりセル層の垂直積層によって容量を確保する3D構造が主流となり、すでに200層を超える製品が登場しています。
また、同様の動きはDRAMにも波及しており、今後は高密度・高速・省電力を実現するための3次元化が重要な開発課題となる見込みです。これらの立体構造技術は、今後の半導体進化を支える鍵といえるでしょう。
3D NANDへの移行とその背景
NANDフラッシュメモリは、データを電気的に書き込み・消去できる不揮発性メモリとして広く利用されてきました。かつては、トランジスタセルを平面上に並べるプレーナ型構造が主流でしたが、2010年代初頭から急速に限界が見え始めました。特に15nm世代に差し掛かる頃には、セル間の干渉や電荷の保持性能の低下、絶縁膜の劣化といった課題が顕在化し、単純な微細化による容量増加が困難になりました。
こうした背景から2013年以降、NANDフラッシュは平面から垂直方向への拡張、すなわち「3D NAND」への移行が本格化しました。3D NANDでは、メモリセルを積層することで、セル面積を維持したまま高密度化が可能となり、信頼性や書き換え耐久性の面でも大きな改善が得られます。当初は32層から始まったこの技術も、現在では200層を超える製品が実用化されており、大容量ストレージや高速アクセスを必要とする分野で不可欠な技術基盤となっています。
積層層数の増加と周辺回路の微細化
3D NANDの進化は、単なるセルの垂直積層だけでなく、その周辺回路の高度な最適化と密接に関係しています。2010年代初頭には24層や32層といった構造が主流でしたが、現在では200層を超える製品が商用化されており、開発競争は240層以上へと移行しつつあります。セルを縦に積むことで面積当たりのビット密度を飛躍的に高める一方、セル構造そのものも「チャージトラップ型」などへと進化し、書き換え耐久性や電力効率も改善されています。
さらに重要なのが、セルを制御・管理する周辺回路の微細化とレイアウト最適化です。3D NANDでは、セル領域とは別に、アドレスデコーダや読み書き制御回路などの周辺回路が配置されており、その微細化が進むことで、より多くのメモリセルを限られたパッケージ内に搭載することが可能になります。加えて、周辺回路の設計には高電圧トランジスタや耐熱性のある材料も求められ、各社は設計技術と製造プロセスの両面で競争しています。
このように、セル層数の拡張と周辺技術の最適化は表裏一体の関係にあり、3D NANDの高性能化と省スペース化を支える要素として不可欠です。データセンターからスマートフォンまで、あらゆるデバイスで大容量メモリの需要が高まる中、今後も積層技術と周辺回路の進化が鍵を握ることは間違いありません。
DRAMの3D化も今後の鍵
DRAMは長年、微細化によって記憶容量や動作速度の向上を実現してきましたが、近年はトランジスタとキャパシタの寸法限界に直面しつつあります。特にキャパシタの体積を維持しながらセル面積を縮小することが難しくなり、従来のプレーナ型(平面構造)では電荷保持能力やリフレッシュ頻度の面で課題が顕在化しています。このような背景を受け、フラッシュメモリに続く形で、DRAMにも3次元構造の導入が本格的に検討され始めています。
3D DRAMでは、セルアレイや周辺回路を垂直方向に積層し、メモリ密度を大幅に向上させることが可能となります。これにより、単位面積あたりの容量拡張だけでなく、信号の伝送距離が短縮されることで、動作速度やエネルギー効率の改善も期待されています。現在、韓国や米国の大手メモリメーカーが、数十層規模の試作を進めており、製品化のめども徐々に見え始めています。
また、従来のワンチップ内集積に代わり、ロジック部とメモリ部を異なるプロセスで製造して垂直方向に接続する「ハイブリッドボンディング技術」も注目されています。この方式では、最適な材料や構造を柔軟に選べるため、製造歩留まりや性能の面で大きな利点があります。
今後、AIやビッグデータ処理の分野で求められる超高速・大容量のメモリ需要に応えるには、DRAMの3次元化は避けて通れない課題となるでしょう。微細化の限界を突破するための次なる一手として、業界の期待が集まっています。
まとめ
半導体業界では、微細化の限界を補うために構造や設計手法の転換が加速しています。チップレット技術は、異種チップを柔軟に組み合わせることで高性能化と製造効率の両立を可能にし、既に実用化が進んでいます。また、メモリ分野では3D NANDを中心とした積層技術が標準化され、DRAMにも立体構造の波が及び始めています。
今後は、これらの高度な集積技術と、設計最適化・ソフトウェアとの連携によって、さらなる高性能・省電力な半導体の開発が進展することが期待されます。